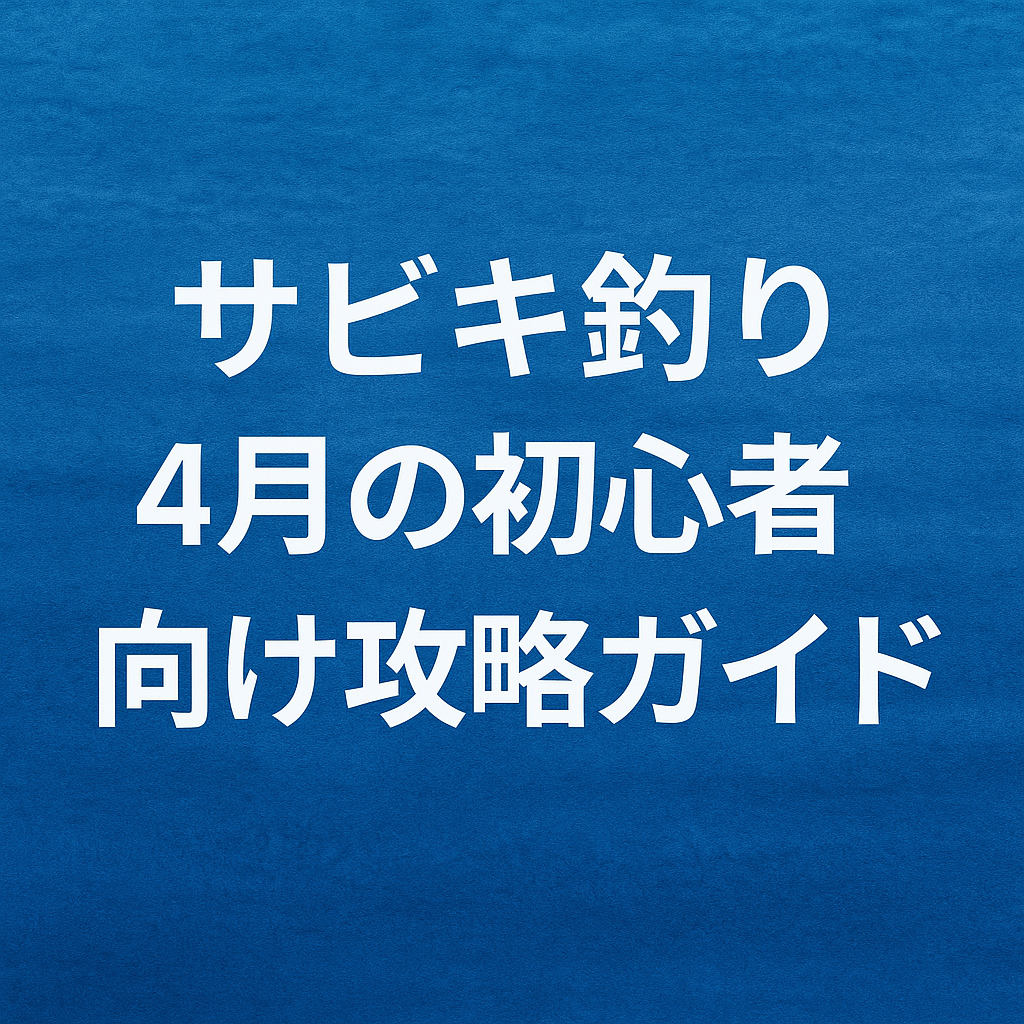
春の暖かさが増す4月は、いよいよサビキ釣りのシーズンが本格化し始める時期です。4月のサビキ釣りではどんな魚が釣れるのか、どのような釣り方が効果的なのかを知りたい方も多いはずです。
本記事では、4月にサビキ釣りで釣れる魚の特徴や、釣果を伸ばすためのポイントを詳しく解説します。3月の厳しい寒さが和らぎ、5月のベストシーズンに向けた“準備の月”とも言える4月は、地域によって釣れる魚や釣果の安定度に差が出やすいのも特徴です。
「サビキ釣りは何月まで楽しめるの?」といった疑問や、春に釣れないときの対策、また関東で春に人気の海釣りスポットなども取り上げていきます。これから釣りを始める春の初心者にも分かりやすい内容を心がけていますので、ぜひ参考にしてみてください。
- 4月にサビキ釣りで釣れる代表的な魚の種類
- 春の気候や水温が釣果に与える影響
- 釣れない時の具体的な対策方法
- 関東で4月にサビキ釣りを楽しめる場所
サビキ釣りで4月に釣れる魚と注意点

- 4月にサビキ釣りで釣れる魚とは
- 4月の釣りで釣れない原因と対策
- 春のサビキ釣りは初心者にも最適
- 関東で楽しめる春の海釣りスポット
4月にサビキ釣りで釣れる魚とは

4月は、サビキ釣りで釣れる魚が徐々に増え始める季節です。代表的な魚にはアジ、イワシ、サバがあり、タイミングや場所を選べば、数釣りも十分に楽しめます。
この時期の魚は、水温の上昇に伴って沿岸部へ回遊してきます。特にアジは、湾内に入り始める時期で、サイズは15〜20cm程度の中型が中心です。イワシやサバも群れで行動するため、一度魚が寄れば連続して釣れることも珍しくありません。
例えば、朝や夕方の「マヅメ時」に釣りをすることで、魚の活性が高くなりやすく、短時間で釣果を上げられる可能性が高まります。また、潮通しの良い堤防や海釣り公園などは魚の回遊が期待できるポイントです。
ただし、地域や日によってはまだ魚の数が少ないこともあります。魚の群れがいない場所では、いくら撒き餌をしても釣れにくいため、事前に釣果情報を確認して釣り場を選ぶことも重要です。
4月は本格シーズン突入前の“準備期間”とも言えるため、釣れる魚の種類や数は日によって差があります。とはいえ、条件が揃えば春の陽気の中で楽しく釣りを楽しむことができます。
4月の釣りで釣れない原因と対策

4月のサビキ釣りで「思ったより釣れない」と感じる原因はいくつかあります。主な理由として、水温がまだ低めであること、魚の回遊が安定していないこと、そして狙う層(タナ)がずれていることが挙げられます。
この時期、陸上の気温は春らしく暖かくなりますが、海水温はそれほど変わっていません。特に朝や夜は冷たいままなので、魚の活性が低くなりがちです。そのため、魚の群れが岸まで寄ってこない日もあります。
例えば、堤防の足元に魚が見えない場合は、ウキを使って少し沖を狙うと反応が出ることがあります。また、魚の泳層は日によって異なるため、表層から中層、底付近まで順番に探ってみることが効果的です。
さらに、釣れないときは針のサイズやサビキの素材を変えるのも有効です。小型の魚が多い時期は、細めのハリ(2~4号)を使うと食いが良くなることがあります。
釣果を上げるには「魚がいないから釣れない」のではなく、「釣れる条件をうまく探す」ことがポイントです。釣れない時間帯や状況にも柔軟に対応できれば、4月でもしっかりと釣果を狙うことができます。
春のサビキ釣りは初心者にも最適
春のサビキ釣りは、これから釣りを始める初心者にとって非常に取り組みやすい釣り方です。使用する道具がシンプルで、操作も難しくないため、経験がなくても安心して挑戦できます。
この時期は、アジやイワシなどの小型回遊魚が堤防や岸壁に寄ってくるため、足場の良い場所から手軽に釣果が期待できます。特に朝夕の短時間に集中して釣れる「時合(じあい)」があるので、短い時間でも楽しめます。
例えば、3〜5メートルのサビキ竿に、アミエビを詰めたコマセカゴをセットするだけで準備は完了です。あとは仕掛けを海に落とし、竿を軽く動かして魚が寄ってくるのを待つだけ。魚がかかれば複数匹を一度に釣り上げることも可能です。
ただし、魚の口に合わない大きさの針を使ってしまうと、かかりにくかったりバラしやすくなったりする点には注意が必要です。針のサイズは釣れる魚の大きさに合わせて選びましょう。
春の穏やかな天候と重なり、外でのレジャーにもぴったりです。親子や友人同士での釣行にも適しており、釣りの楽しさを知る良いきっかけになります。
関東で楽しめる春の海釣りスポット
関東には、春にサビキ釣りを楽しめる海釣りスポットが多数存在します。中でも足場が良く、トイレや駐車場が整備された場所は初心者やファミリーにも人気です。
たとえば、神奈川県の「本牧海づり施設」は、アジやイワシが春先から狙える定番の釣り場です。海に突き出した桟橋スタイルで潮通しが良く、釣果が安定しています。
千葉県では「市原海釣り公園」がオススメです。こちらもアミエビを使ったサビキ釣りで実績があり、レンタル用品も充実しているため、道具を持っていない人でも手軽に楽しめます。
また、東京都内でアクセスが良い場所としては「若洲海浜公園」があります。都心からの移動がしやすく、堤防も広いため混雑していても釣りがしやすい点が魅力です。
ただし、人気スポットは休日や大型連休になると大変混雑することがあります。混雑を避けたい場合は、平日の午前中や、気温が安定した日の午後を狙うと比較的空いています。
このように、関東近郊には初心者でも安心してサビキ釣りを楽しめる場所がたくさんあります。事前に施設のルールや釣果情報を調べておけば、より充実した釣行になります。
サビキ釣り 4月の魅力とシーズン情報
- サビキ釣りは何月まで楽しめる?
- サビキ釣りのベストシーズンはいつ?
- 3月と5月の釣果比較と違い
- 4月の釣行で準備すべき道具とは
- 春の釣果アップに効く釣り方のコツ
- サビキ釣り 4月の特徴と押さえておきたいポイントまとめ
サビキ釣りは何月まで楽しめる?
サビキ釣りは、主に春から秋にかけて楽しむことができ、多くの地域では11月頃までが一つの目安となります。気温の低下とともに水温も下がり、魚の活性が落ちるため、冬に入ると釣果は安定しにくくなります。
この釣り方の対象となる小型回遊魚は、水温が高い時期に沿岸まで近づいてくる習性があります。特にアジやイワシ、サバなどは夏から初秋にかけて岸近くに回遊してくることが多く、サビキ釣りが最も盛り上がる時期となります。
例えば、関東近郊では、早いところで3月下旬から釣果情報が出始め、11月中旬頃まで安定した釣りが楽しめます。ただし、地域差やその年の気候条件によって若干前後することがあるため、事前に釣具店や釣り施設の情報を確認するのが安心です。
寒くなると魚が深場へ移動してしまい、堤防などの浅場では釣れにくくなります。どうしても冬にサビキ釣りをしたい場合は、温排水が流れる港湾や、海水温が安定している場所を探す必要があります。
つまり、サビキ釣りは年間を通して完全にできないわけではありませんが、多くの人が快適かつ効率よく楽しめるのは春から晩秋までの期間です。
サビキ釣りのベストシーズンはいつ?

サビキ釣りのベストシーズンは、魚の回遊が活発になり、気候も安定する「初夏から秋口」にかけてです。特に6月〜9月は魚種・数ともに豊富で、初心者でも釣果を上げやすい時期といえます。
この時期は、水温が高く魚の活性が最も高まるため、岸からでも十分に魚が狙えます。朝夕の涼しい時間帯には群れが岸近くに集まりやすく、一度に数匹釣れることも珍しくありません。
例えば、夏場は豆アジやカタクチイワシなどの小型回遊魚が多く、群れで回遊するために釣りやすくなります。また、波が穏やかな日が多く、風の影響を受けにくいのもサビキ釣りに向いているポイントです。
一方で、秋になると魚のサイズが大きくなる傾向があり、数よりも型狙いにシフトしていきます。9月から10月にかけては、20cm以上のアジが釣れることもあり、引きの強さを楽しめるシーズンです。
ただし、真夏の昼間は日差しが強く、釣り人にも魚にも負担がかかります。暑さ対策やこまめな水分補給は欠かせません。快適に釣りを楽しむには、早朝や夕方の時間帯を選ぶのがおすすめです。
このように、サビキ釣りは長期間楽しめますが、魚の動きと釣りやすさを考えると、初夏から秋が最も適したシーズンと言えるでしょう。
3月と5月の釣果比較と違い
3月と5月では、サビキ釣りの釣果や魚の活性に明確な違いがあります。気温と海水温の上昇が釣果に大きく影響するため、釣りやすさにも差が出やすい時期です。
まず3月は、海水温がまだ低く、魚の動きが鈍いため、堤防などの浅場に回遊してくる魚は限られます。特にアジやイワシなどの回遊魚は外洋に留まっていることが多く、釣果が安定しにくい傾向にあります。魚が寄らない時間が長く、釣れない時間が続くことも珍しくありません。
一方、5月になると水温が上がり、多くの魚種が本格的に湾内へ入り始めます。サイズも徐々に大きくなり、豆アジに加えて中型のアジやサバも混ざるようになります。また、サビキ釣り特有の「群れで一気に釣れる」場面も増えるため、初心者でも楽しみやすくなります。
例えば、同じ釣り場でも、3月は1日粘って数匹だったのが、5月には短時間で十数匹釣れるというような違いが出ることもあります。
このように、気象条件や水温の差が釣果に直結するため、どの月に釣りをするかによって、得られる体験も大きく変わってきます。
4月の釣行で準備すべき道具とは
4月のサビキ釣りに出かける際は、季節の特徴に合った道具を準備しておくことで、釣果の安定と快適な釣行につながります。春は天候が変わりやすく、魚の活性も日によって波があるため、道具選びが重要になります。
まず必要なのは、全長3〜5m程度の万能竿や磯竿です。堤防や岸壁からの釣りがメインになるため、操作しやすい長さの竿を選びましょう。竿に合わせて、2500〜3000番のスピニングリールをセットし、道糸は2〜3号のナイロンラインがおすすめです。
仕掛けは、魚皮やスキン素材が付いたサビキ仕掛けを用意します。魚のサイズに合わせて、ハリの号数も選んでおくと便利です。アジやイワシがメインターゲットなら、3〜5号程度が使いやすいでしょう。
そして、マキエカゴに入れるアミエビは必須です。冷凍ブロックタイプを使う場合は、事前に解凍しておく必要があります。手軽さを求めるなら、チューブ式の常温保存タイプも便利です。
他にも、吸い込みバケツやマキエスプーンがあると、餌の補充がスムーズに行えます。また、予備の仕掛けやカゴを持っていくことで、トラブル時の対応も安心です。
春特有の冷たい風や急な天候の変化にも備え、風よけの上着や雨具も忘れずに持参すると良いでしょう。釣果だけでなく、快適さを左右するポイントになります。
春の釣果アップに効く釣り方のコツ

春のサビキ釣りで釣果を伸ばすには、いくつかのポイントを意識することが大切です。気温に比べて海水温が低く、魚の動きが不安定になりやすい春だからこそ、工夫次第で釣果に差が出ます。
まず意識したいのは「タナ(魚の泳ぐ層)」の見極めです。魚は海面近くから底付近まで、日や時間帯によって泳ぐ深さが変わります。仕掛けを投入しても反応がない場合は、タナを変えて探ってみましょう。アジは中層〜底層、イワシやサバは比較的上の層にいることが多いです。
次に大切なのが「撒き餌のタイミングと量」です。魚を寄せるには、こまめにアミエビを補充して撒くことが効果的です。ただし、過剰に撒きすぎると魚が満腹になって針にかかりにくくなるため、適量を意識しましょう。
また、魚が1匹かかった時にすぐ引き上げず、少しだけ仕掛けをそのままにしておくと、群れの中で「追い喰い」が発生しやすくなります。これにより一度に複数匹を釣ることができる可能性が高まります。
釣り場選びも釣果に大きく関わります。潮通しが良く、回遊魚が寄りやすい場所を選ぶことが重要です。釣果情報を確認した上で、朝夕の時間帯を狙うと、より効果的です。
このように、タナの調整、撒き餌の工夫、追い喰いの誘発、時間帯の見極めといった基本を丁寧に意識することで、春でもしっかり釣果を上げることができます。
サビキ釣り 4月の特徴と押さえておきたいポイントまとめ
記事のポイントをまとめます。
- 4月はアジ・イワシ・サバなどが釣れ始める季節
- 魚の回遊は日によってムラがある
- 朝夕のマヅメ時が釣果を伸ばしやすい時間帯
- 湾内や潮通しの良い堤防が狙い目
- 水温が低く魚の活性が安定しない日もある
- 魚が釣れない時はタナを変えて探ると良い
- 細めのハリを使うと小型魚に有効
- 撒き餌の量とタイミングの調整が釣果に直結
- 追い喰いを誘うことで一度に複数匹釣れる可能性がある
- サビキ釣りは初心者でも取り組みやすい
- 春は穏やかな気候でファミリーフィッシングにも最適
- 関東では本牧、市原、若洲などが人気スポット
- サビキ釣りの本格シーズンは6月〜9月
- 4月はシーズン序盤の準備期間と位置づけられる
- 釣行前に地域の釣果情報を確認しておくのが効果的
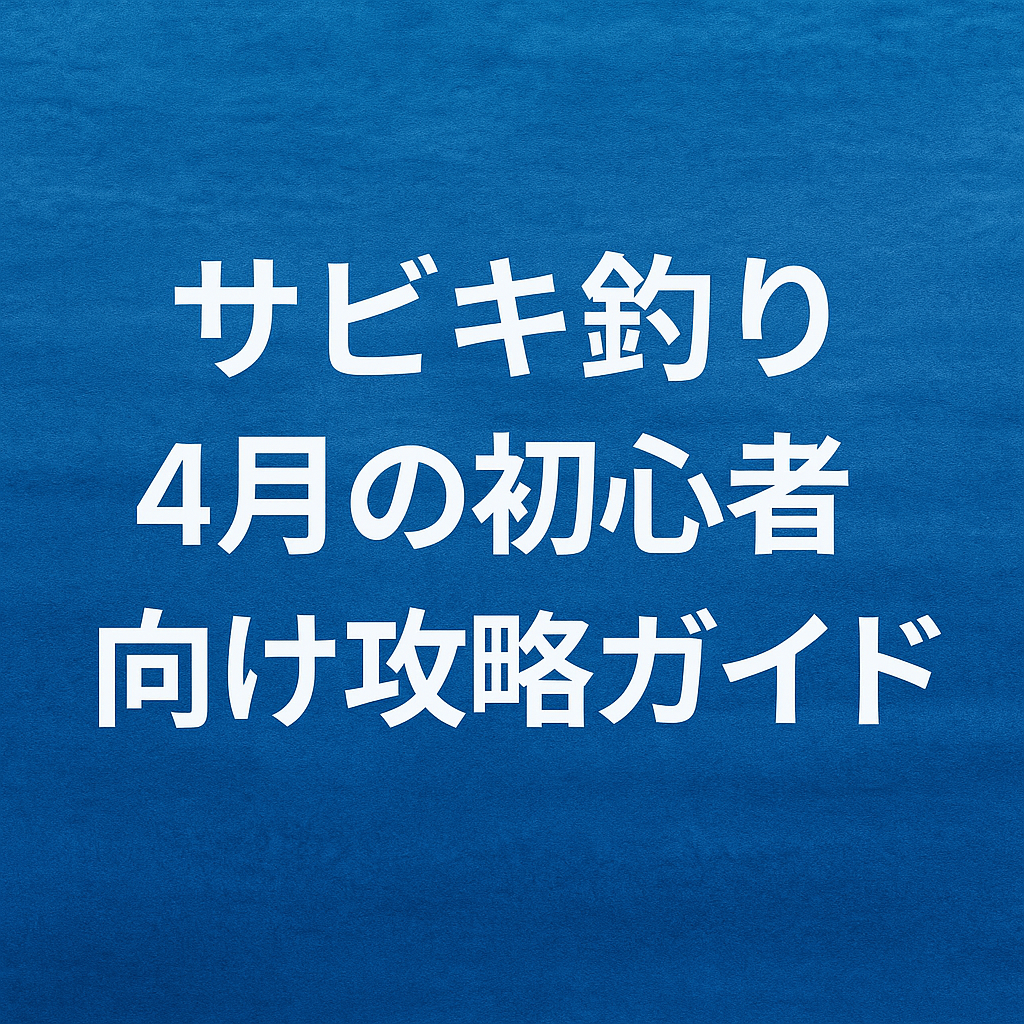

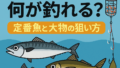
コメント